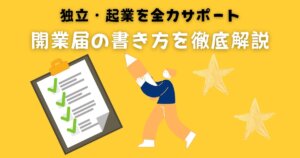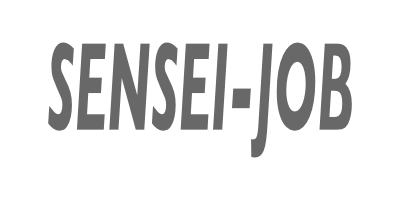こんにちは、元教員起業家の「りっぽん」です。
教員を辞めることを決意したけど、どんな流れで退職すれば良くわからないものです。
ましてや、一般企業とは違い周りの教員も退職した経験がない人がほとんどで聞けません。
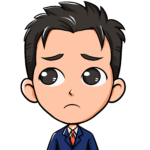 中堅くん
中堅くんついに来年退職するぞ!でもスムーズに退職するにはどうしたらいいのだろうか…。
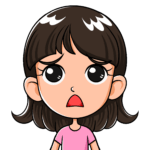 りっぽん
りっぽん確かに退職に必要な書類や手続きって何があるのかわからないよね。特に初めての場合なんか。
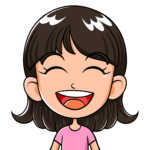 りっぽん
りっぽん起業を勢いよく始めるためにも、退職手続きをスムーズに終わらせよう!
退職届や退職金申請など、教員を辞めるときには色々なことをする必要があるので失敗しないためにも必要なものや手順を説明していきます。
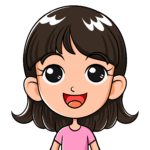 りっぽん
りっぽん退職までの全体の流れを把握しておくと、すごく安心するよ〜
教員を辞める意向を管理職に伝えましょう。最低でも退職日の1〜3ヶ月前には伝えておくことで、スムーズに退職することができます。口頭で伝えるだけでなく「退職願」を提出して意思表示をしましょう。
教育委員会指定の書式で「退職届」を提出します。退職願は却下されることのない書類ですので、提出した段階で「退職」が確定します。
学校の事務員から受け取った「退職金の書類」から退職金を請求します。
学校の事務員から年金に関する書類を受け取り、最寄りの自治体に提出します。
健康保険の切り替えは、転職先が決まっていればそこの健康保険組合に加入します。転職先が決まってない、もしくは個人事業主になる場合は、①現在加入している共済組合を任意継続する。②自分が住んでいる市町村の国民健康保険に加入する。③家族の健康保険に加入する。の3パターンです。
退職までに、業務の引き継ぎをしておく必要があります。特に書類関係の引き継ぎができていないと、退職後に連絡がくる場合があります。紙媒体だけでなく、データの引き継ぎも忘れずにしましょう。
退職日を迎えると、晴れて「退職」となります。事業主として生活する「第一歩」です。
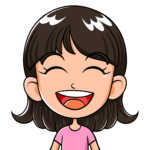 りっぽん
りっぽんそれでは各STEPごとに詳しくみていこー!
- 「退職届の書き方」や「提出するタイミング」がわかる
- 「退職金」の申請に必要な書類や方法がわかる
- 公的年金や健康保険の手続きがわかる
- 退職時に必要な「引き継ぎの方法」がわかる
「退職の手続き」は辞める時にすごくめんどくさいし、何をしていいかも分からないことが多くあります。本記事で、必要な書類や手順を参考にしてください。
また当ブログでは退職前に次のステップを決めていることをオススメしています。
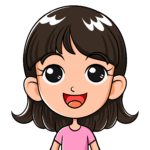 りっぽん
りっぽん転職や起業だね!
リスクを最大限に抑えつつ退職するためにも、次のステップが決まっていない場合は教員の「副業」から「起業」までを徹底解説!教員に依存しない働き方を参考にしてください。
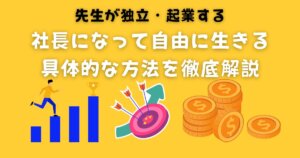
STEP1: 管理職に「教員を辞める」意向を伝える
 りっぽん
りっぽんまず初めに、退職する意向を伝えなきゃね。
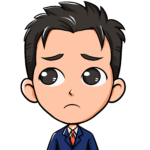 中堅くん
中堅くんでも、教員の場合は誰に伝えればいいの?
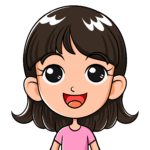 りっぽん
りっぽん人事調書(個人調書)を提出するタイミングで退職の意志を管理職に伝えるよ!
地域によって違いはありますが、人事面談・個人面談など、来年度の動きを確認する時に伝えるのがベストです。
教員を辞めることを決意した時にまず初めにしなければいけないことは、「退職の意向を伝える」です。
一般企業と同じように、教員も退職の意向を伝えるのは管理職です。
- 校長先生
- 教頭先生
- 学年主任(必要ないことが多い)
一般企業と同じく、退職日の1〜3ヶ月前には伝えておく方が良いと言われています。
ただ、教員が退職を伝えるベストのタイミングは11月です。
地域によっては違いはあると思いますが、人事調書を提出するタイミングで退職の意向を伝えると、相手側も翌年の人事異動といった面で円満にことが進むかと思います。
体調面などでやむをえない場合を除き、ギリギリに伝えるのは避けましょう。
STEP2: 退職願と退職届を提出する
 りっぽん
りっぽん次は退職願と退職届を書いていこうか!
退職願と退職届を提出する流れ
① 校長先生に退職願を提出する
校長先生と教頭先生に退職の意向を伝えるタイミングで、退職願を提出します。
校長先生と教頭先生、3人で同時に話すときはその場で渡せばいいのですが、別々で話す場合は校長先生に提出してください。
〜「退職願」と「退職届」の違い〜
| 役割 | |
| 退職願 | 退職の意思を伝えるもの。(この段階ではまだ退職は正式には決まってはいない)*必ずしも書面での退職願は必要ないが、退職の意思が固いことを示したり、学校側に退職の申し入れをした根拠になったりします。 |
| 退職届 | 正式に退職することを伝えるもの。*学校の管理職に渡すのではなく、各都道府県の教育委員会に提出します。 |
手書きでも、パソコンでタイピングして印刷したものでも大丈夫です。
①記入した日付
②学校名
③校長名
④学校名
⑤自分の名前
⑥押印
⑦理由(私儀だけでOK)
⑧退職希望日
退職願を入れる封筒の書き方
①学校名
②自分の名前
*出さなくてもいいがあったら便利なもの
→退職願と一緒に、退職理由を詳細に説明した1枚分くらいの書面を同封しておけば退職理由を詳しく聞かれないというメリットがあります。
また、教育委員会での面談の際にもその書面があれば、スムーズに進むことがあります。
② 校長先生より、書式が決まっている教育委員会に提出する退職届を受け取り記入
退職届は退職願と違い、各都道府県の教育委員会ごとで書式が違うので各自治体の書き方に合わせて記入してください。
基本的には退職願と同じような内容で、退職する旨を伝えた書類になります。
STEP3: 退職金の請求
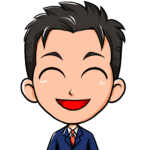 中堅くん
中堅くんさて、退職届も出したし、退職金を何に使おうかな〜
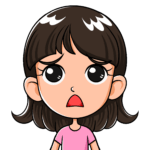 りっぽん
りっぽん意外とみんな知らないことだけど、退職金は請求しないともらえないのよ!
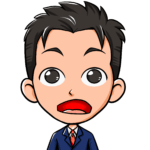 中堅くん
中堅くんえ!? そうなんですか? やり方を教えてください…。
退職届を提出したら、次は学校の事務員から受け取った「退職金の書類」を提出します。
退職金は、実は請求しないともらえないです。基本的に退職の意向をつたえた管理職が事務へ伝達し、書類を準備してくれます。
ただ、万が一のこともあるのでちゃんと確認し請求を忘れないようにしましょう。
退職金は、退職日の次の月の給料日に振り込まれることが多いです。
例え: 3月末退職なら4月の給料日に受け取り
STEP4: 公的年金
退職時にややこしい手続きの一つが「公的年金」です。
働いているときは、学校の方で全て任せておいて、給与から自動的に天引きされてとても簡単だったと思います。
ですが、これから個人事業主として働く人や次の転職先まで期間がある人は国民年金の「第1号被保険者」となり変更の手続きと保険料の支払いをしなければいけません。
引用元:日本年金機構 (会社を退職した時の国民年金の手続き)
詳しくはここでは割愛しますが、事務の人から書類を渡されるのでその指示に従い記入して提出してください。
STEP5: 健康保険
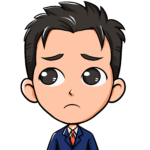 中堅くん
中堅くん退職したら、保険証を返してって言われたんだけど。病気になったらもしかして全額負担するの!?
 りっぽん
りっぽん公的年金と同じで、辞める時に健康保険の切り替えも必要だよ!
健康保険の切り替えは、転職先が決まっているかどうかで対応が変わります。
転職先が決まっている場合
転職先がすでに決まっているのであれば、その企業や団体の健康保険組合に加入します。
転職先の指示に従い書類を提出してください。
転職先が決まっていない、個人事業主になる場合
退職から次の職場への入社まで期間があったり、個人事業主になる場合だと、自分で健康保険をどうするか決めなければいけません。
- 現在加入している共済組合を任意継続する
- 自分が住んでいる市町村の国民健康保険に加入する
- 家族の健康保険に加入する
のうちどれかを選ぶことになります。
③はいわゆる扶養にはいるので、保険料がかからないことが多いです。
①と②は追加で費用がかかるので注意しなければいけません。
国民健康保険の保険料は、住んでいる地域や前年の所得などによりますが、東京都に住み前年度の年収が500万円だった場合、保険料は月々49,050円になります。
引用元:全国健康保険協会 令和4年度保険料額表
STEP6: 引き継ぎ
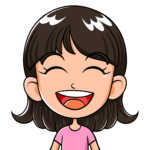 りっぽん
りっぽん退職するための書類を提出したら、あとは後任の先生方のために引き継ぎをちゃんとしないとね!
次の先生が困らないように書類を整理したり、手順を可視化したりしておくといいですね。
特に書類関係の引き継ぎがちゃんとできていないと、退職後に連絡がきて対応するはめになります。
紙媒体だけでなく、データの引き継ぎも忘れずにしましょう!
もし次の担当する先生がわかっている場合は、直接会って説明するとわかりやすいかもしれませんね。
STEP7: 教員を辞める(退職)
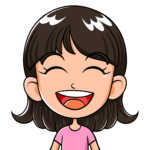 りっぽん
りっぽん退職日を迎えるとこれで晴れて、退職だよ!
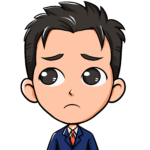 中堅くん
中堅くんでも、退職するのにこんなにも手続きがあってちゃんとできるか不安です。
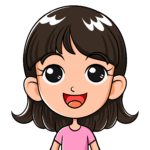 りっぽん
りっぽん大丈夫!退職の手続きに慣れていない人がほとんど!
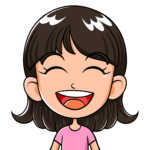 りっぽん
りっぽんだから、丁寧に事務の人に説明をお願いするとちゃんと教えてくれるから安心して!
退職届から退職金まで知っておくべきことまとめ
本記事では、「教員を退職するときに必要な手続き」について詳しく解説してきました。
STEP1: 管理職に退職の意向を伝える
STEP2: 退職願と退職届を提出する
STEP3: 退職金の請求
STEP4: 公的年金
STEP5: 健康保険
STEP6: 引き継ぎ
STEP7: 退職
次の一歩へスムーズに進むためにも、退職の手続きをサクッと終わらせて自分のやりたいことに時間をたっぷり使っていきましょう。
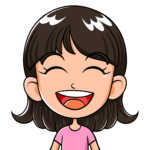 りっぽん
りっぽんフリーランスになる人は「開業届」も忘れずにね!
個人の力で稼ぐ人は「開業届」の提出をすることで、税金面で優遇されます。
開業届の作成については個人事業主になったときに必要な「開業届の書き方」を徹底解説で詳しく解説しています。参考にしてください。